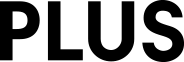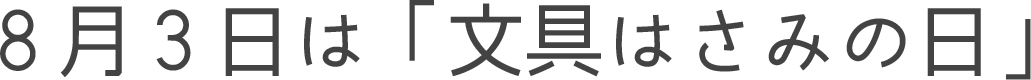浅草にある演芸場で漫談をしていた際、「なにか一つ、自分の芸を持ちたい」と思い始めたことがきっかけで紙切りの世界に飛び込んだという、はさみ家紙太郎さん。下絵を描かず、即興で様々な形に紙を切り出す鮮やかなはさみ捌き、伝統芸の美しさに一目ぼれして、紙切りの名人・泉たけし師匠に弟子入りを決意したのが13年前。どっぷりと魅せられた、紙とはさみがつむぐ伝統芸の世界について語っていただきました。
師匠から託された“道具”という命
紙太郎さんが使っているのは、日本製の「長太郎(東鋏*:とうばさみ)」という裁ちばさみです。もともとは布を裁つための道具ですが、紙太郎さんにとっては紙切り専用。
なかでも愛用している一本は、なんと師匠が50年以上も使ってきたものなのだそう。「もちろん、どんなはさみでも紙は切れますよ。でもやっぱり、このはさみが1番しっくりくるんです。師匠の想いがこもっていて、大切な1本なんです」と話してくれました。

東鋏は、実は日本刀を作る刀鍛冶の技術を応用して作られているはさみ。刃の金属がとても丈夫で、研ぎさえ続ければ何十年も使い続けられるのが特長です。
紙太郎さんは、年に1度はさみを研ぎに出し、ふだんは椿油でていねいに手入れをしているそう。「はさみは一度落としてしまうと、刃の調子が狂っちゃうんです。だから絶対に落とさないように気をつけています」とのこと。

そしてもう1つ、大事にしているのが“紙しか切らない”というこだわり。「たとえ洋服のタグに付いてるプラスチックの紐でも、切りません」とキッパリ。
道具に対する丁寧な姿勢と敬意が、紙太郎さんの芸の芯にしっかりと根付いています。
*「東鋏」は、株式会社庄三郎の登録商標です。
形を生み出す「無描の技」──絵を描かずに切る、その極意
「どうして下書きもせずに切れるの?」とよく聞かれるんですが、実は紙切りって、絵を描かずにいきなり紙を切っていく芸なんです。だからこそ、“型”と“比率”の感覚がとても大事になってきます。

たとえば動物を切るとき。顔の大きさは紙の3分の1、鼻はこの辺…といったように、紙全体の中でのバランスを頭の中でイメージしながら、パーツを配置していくんです。一見、即興に見える作品も、実はこうした構造的な“考え方”に支えられているんですね。
それから、紙切りに欠かせないもうひとつの技術が「紙を動かす」こと。細かい部分や曲線を切るときには、はさみを動かすよりも、紙そのものを滑らせたり、回したりしながら形を作っていきます。
「力で無理に切るんじゃなくて、紙と会話するように動かすんです」と紙太郎さん。この“紙を動かす感覚”は、まさに師匠から教わって、舞台の経験の中で磨かれてきた知恵なのだそうです。
紙の折り方や切り始める順番も、すべてが工夫の積み重ね。
繰り返し実践して生まれた“再現できる技術”として、しっかりと受け継がれています。
切る、だけじゃない。観る者とともに創る

会話をしながら切る。それも紙切りの楽しさです。紙太郎さんの紙切りは、ただ紙を切るだけではありません。お客さんとの“会話”も、芸の大切な一部になっています。
「黙って切っていると、ちょっと思い詰めてる人みたいに見えちゃうんですよ(笑)」と紙太郎さん。だからこそ、おしゃべりを交えながら、楽しい雰囲気で進めているそうです。
たとえば何を切っているのかをクイズにしたり、ちょっとした小話を挟んだり。パンダを切るときには、「パンはパンでも、食べられないパンです」なんてユニークなヒントで、観客を引き込みます。
はさみの音と、言葉のリズムがぴったり重なるその瞬間。舞台の上には、まるで魔法がかかったような空気が流れます。
技術の継承と、紙切り芸の未来
「即興の紙切り芸って、日本にしかないそうなんですよ」と紙太郎さんは話します。
その場でお題をもらい、即興で紙に形を描き出す——紙切りの魅力は、熟練の技とひらめきのバランスにあります。
いわば、“形を記憶する頭”と“紙と対話する感覚”のかけ算。はさみ1本で作品を生み出すこの芸は、とてもシンプルでいて、奥が深いのです。
「海外の方にも、もっと紙切りを知ってもらえたら嬉しいですね」と、発信への想いも強く持たれています。
今、紙切り芸人は日本全国で13人ほど。「弟子を取るかどうかはタイミングだと思っています。数を増やすことが目的じゃないですから。でも、“受け継ぎたい”と思ってくれる人が現れたら、そのときはきちんと渡せるようにしておきたいですね」と語ってくれました。
“一丁のはさみ”に込められた魂

紙太郎さんが使うはさみには、金色の塗装やキラリと光るラインストーンが施されています。
これは、かつて師匠が「夜のステージでも遠くから輝いて見えるように」と工夫してつけたものだそうです。
いまでも紙太郎さんは、そのはさみを手に舞台に立ち続けています。
そこには、師匠から受け継いだ意志とちょっぴりユーモラスな心、そして芸への誇りがしっかりと息づいています。
「はさみは、もう“相棒”ですね。芸の道具であると同時に、師匠との絆なんです」
紙の上をすっとなぞる東鋏の刃先。
そのひと振りひと振りには、積み重ねてきた時間と技術、そして何より心が込められています。
紙切りとは、ただ紙を切るだけではありません。
そこには、日本らしい美意識と、静かな情熱を感じることができる——そんな奥深い芸の世界が広がっていました。
▼はさみ屋紙太郎さんインタビューの様子はこちら